$\S3.4$平行ベクトル場の角度差
ベクトルの曲線に沿った平行移動による微分の定義と共変微分商が一致することが示された.
ここで,曲面上に2点$A,B$を与えたとき,2点を結ぶ曲線によって平行移動は異なることに注意する.
すなわち,2点$A,B$を結ぶ曲線を$C_1,C_2$とすると,$A$におけるベクトル$X$を$C_1,C_2$に沿って平行移動したときのベクトルをそれぞれ$Y_1,Y_2$
とすると,一般に$Y_1,Y_2$は異なる.
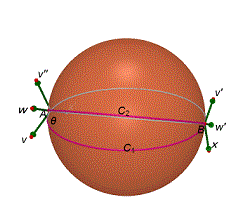 半径$1$の球面で考える.
半径$1$の球面で考える.
曲線に沿った2つの平行ベクトル場はなす角を変えない.
測地線の接ベクトルは平行ベクトル場.
の2つの性質を利用する.
2点$A,B$を単位球面の対蹠点,$A,B$を通る大円弧を$C_1,C_2$,さらに$C_1,C_2$のなす角を$\theta$とする.
$C_1,C_2$の点$A$における接ベクトルをそれぞれ$v,w$,点$B$における接ベクトルをそれぞれ$v',w'$とする.
このとき,$v$の$C_1$に沿った平行ベクトル場の$B$におけるベクトルは$v'$,
一方,$v$の$C_2$に沿ったベクトル場の$B$におけるベクトルは$x$で,$v',x$は異なる.
それでは,$v$を曲線$C_1$に沿って点$B$まで平行移動し,その後曲線$C_2$に沿って$B$まで平行移動したベクトルを$v''$
としたときの$v,v''$のなす角を調べましょう.
$C_1$に沿って$v$を平行移動すると$v'$でさらに$C_2$に沿って平行移動すると$v',w'$のなす角と$v'',w$の
なす角は等しいから
$\angle (v,v'')=2\theta$
が成り立つ.ここで$\angle (v,v'')$は$v$から$v''$に向かって測った
角で$\angle (v,v'')=-\angle (v'',v)$である.
$\theta$すなわち2大円弧$C_1,C_2$のなす角が大きくならば一周したときの平行ベクトル場の変化量
$\angle (v,v'')$
が大きくなる.
さらに,$C_1,C_2$の囲む面積の小さい方を$S$とすると,球の半径1より
$S=4\pi \cdot \dfrac{\theta}{2\pi}=2\theta$
さらに,半径が$R$のとき
$S=2R^2\theta$,球の曲率は$\frac{1}{R^2}$
であることに注意する.
球面の小円に沿ってベクトルを平行移動したときの角の変化量を調べよう.
ここで用いるのは
2つの曲面$S_1,S_2$が曲線$C$で接するとき($C$の各点で$S_1,S_2$の接平面が一致する),$S_1$における$C$沿ったに平行ベクトル場は
$S_2$における$C_2$に沿った平行ベクトル場である.
実際,$V(t)$を曲線$C$に沿ったベクトル場とするとき,
$\dfrac{DV(t)}{dt}=(\dfrac{dV(t)}{dt})^T$
で$\frac{dV(t)}{dt}$は$\mathbb{R}^3$における微分で$S_1,S_2$に関係なく$C$だけで決まる.
さらに$( \ \ )^T$は接平面への正射影であるから$V(t)$がいずれかの曲面の$C$に沿った平行ベクトル場なら,もう一方の曲面の
$C$に沿った平行ベクトル場である.
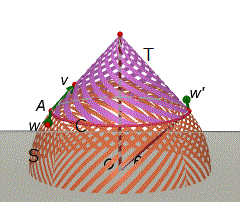 半径1の球面$S$の緯度$\theta$の緯線$C$で接する円錐$T$を考える(右図).
半径1の球面$S$の緯度$\theta$の緯線$C$で接する円錐$T$を考える(右図).
$T$における曲線$C$に沿った平行ベクトル場は$S$における平行ベクトル場でもある.
さらに,ベクトルの平行性は第1基本量だけで決まるから,円錐を展開しても平行性は変わらない.平面の平行ベクトル場は,定ベクトルである
から,円錐面を展開扇形にして,$C$に沿った平行ベクトル場を作り,
逆に円錐に戻し球面に貼り付け,ベクトルのなす角を調べる.
右下図は,円錐の展開図である.
母線の長さが$\frac{\cos \theta}{\sin \theta}$,底円の半径が$\cos \theta$であるから
扇形の頂角は$2\pi \sin \theta$.
円錐の展開図において,$A$におけるベクトル$v$を$C$に沿って平行移動すると$v'$
一方,$A'$で見ると$v$は$v''$であるから$v''$と$v'$の回転角が求めるのである.
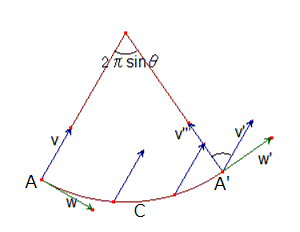 ここで,曲線$C$の接ベクトル$w$に注目する(平行ベクトル場ではない).$w,w'$は円を一周回っているから回転角は$2\pi$.
ここで,曲線$C$の接ベクトル$w$に注目する(平行ベクトル場ではない).$w,w'$は円を一周回っているから回転角は$2\pi$.
したがって,$v''$と$v'$の回転角は
$2\pi -2\pi \sin \theta$
である.
次に,単位球面において緯度$\theta$以上の領域の面積を求めよう.
まず,曲面積の求め方の復習をする.
$U\subset \mathbb{R}^2$のとき,$U$の面積は,$U$を2辺が座標軸と平行な小長方形の和で近似しその小長方形の面積を$S_1,\dots ,S_n$
とする.
$S_1+\dots +S_n \to \iint_Udxdy \ \ (n\to \infty)$
である.
曲面
$\boldsymbol{f}:U\to \mathbb{R}^3$
のとき,曲面$\boldsymbol{f}(U)$の面積は,
$U$を2辺が座標軸と平行な小長方形で近似しそれを$S_1,\dots ,S_n$
とする.
小長方形$S_i$の横を$\Delta x$,縦を$\Delta y$とすると$\boldsymbol{f}(S_i)$はベクトル
$\boldsymbol{f}_x\Delta x,\boldsymbol{f}_y\Delta y$の定める平行四辺形で近似でき,この面積を$S$とすると
$S=|\boldsymbol{f}_x\Delta \times \boldsymbol{f}_y\Delta y|=|\boldsymbol{f}_x\times \boldsymbol{f}_y|\Delta x\Delta y$
ここで
$|\boldsymbol{f}_x\times \boldsymbol{f}_y|^2=|\boldsymbol{f}_x|^2|\boldsymbol{f}_y|^2-(\boldsymbol{f}_x\cdot \boldsymbol{f}_y)^2$
曲面$\boldsymbol{f}$の第1基本量
$E=\boldsymbol{f}_x\cdot \boldsymbol{f}_x,F=\boldsymbol{f}_x\cdot \boldsymbol{f}_y,G=\boldsymbol{f}_y\cdot \boldsymbol{f}_y$
を用いれば
$=EG-F^2$
より
$S=\sqrt{EG-F^2}\Delta x\Delta y$
各$S_i$の面積は$\sqrt{EG-F^2}$倍されるから$\boldsymbol{f}(U)$の面積は
$\displaystyle \sqrt{EG-F^2}S_1+\cdots +\sqrt{EG-F^2}S_n \to \iint_{U}\sqrt{EG-F^2}dxdy \ \ (n\to \infty)$
となる.
当然曲面$\boldsymbol{f}$上の関数$g$の積分は
$\displaystyle \iint g(x,y)\sqrt{EG-F^2}dxdy$
である.
ここで曲面$\boldsymbol{f}(U)$の面積を求めるのに,$\iint_{U}dxdy$と第1基本量$E,F,G$だけで
写像$\boldsymbol{f}$は用いていないことに注意しよう(曲面上の計算が$U$上で行える).
$\sqrt{EG-F^2}dxdy$を曲面$\boldsymbol{f}$の面積要素と呼ぶ.
なお1基本形式$I$を
$I=g_{ij}du^idu^j$
とすると,面積要素は
$I=\sqrt{\det (g_{ij})}du^1du^2$
と表せる.
球面の緯度が$\theta $以上の部分の面積を求めよう.
緯度,経度で球面上の点を表してもよいが($x=r\cos \theta \cos \phi,y=r\cos \theta \sin \phi,z=r\sin \theta$),ここでは球面を
$x^2+y^2+z^2=1 \ \ (z\geqq 0)$
とおいて求める.
$U$を$\mathbb{R}^2$における,原点を中心とする単位円とする.
$\boldsymbol{f}:U\to \mathbb{R}^3,(x,y)\mapsto (x,y,z)$
$x^2+y^2+z^2=1$
より
$z_x=-\dfrac{x}{z},Z_y=-\dfrac{y}{z}$
$\boldsymbol{f}_x=(1,0,z_x)=(1,0,-\dfrac{x}{z}),\boldsymbol{f}_y=(0,1,z_y)=(1,0,-\dfrac{y}{z})$
$E(=\boldsymbol{f}_x\cdot \boldsymbol{f}_x)=1+\dfrac{x^2}{z^2},F=\dfrac{xy}{z^2},G=1+\dfrac{y^2}{z^2}$
したがって
$EG-F^2=\dfrac{1}{z^2}$
より,$\boldsymbol{f}(U)$の面積は
$\displaystyle \iint_{U}\dfrac{dxdy}{z}$
である.
$U$は原点を中心とする半径$\cos \theta$の円である.
$(x,y)$を極座標表示をする.
$x=r\cos \theta,y=r\sin \theta$
のとき
$\dfrac{dxdy}{z}=\dfrac{rdrd\theta}{\sqrt{1-r^2}},0\leqq r \leqq \cos \theta,0\leqq \theta \leqq 2\pi$
より
$\displaystyle \iint_{U}\dfrac{dxdy}{z}$
$\displaystyle \int_0^{2\pi}\int_0^{\cos \theta}\dfrac{r}{\sqrt{1-r^2}}drd\theta$
$=2\pi[-\sqrt{1-r^2}]_0^{\cos \theta}$
$=2\pi (1-\sin \theta)$
これは緯度$\theta$の緯線が囲む面積である.ベクトルが緯線を一周平行移動したときの変化量は,その曲線の囲む面積と一致することがわかる.
次の定理が成り立つことが知られている.半径$1$の球面のガウス曲率が$1$であることを考慮すれ,今まで述べた内容はこの定理の例であることが分かる.
定理
$C$は曲面$S$上の単純閉曲線(途中交わらない閉曲線),$C$の囲む領域は単連結とする.
$C$の弧長による媒介変数表示を
$C:(u^1(s),u^2(s)),s\in [0,d]$
とする.このとき,曲線$C$に沿った平行ベクトル場$X(t)$が曲線$C$を一周したときの$X(0),X(d)$のなす角は
$\displaystyle \iint_DK(u^1,u^2)\sqrt{EG-F^2}du^1du^2$
に等しい.ただし,$K(u^1,u^2)$は$S$のガウス曲率
証明はここでは扱わない.
曲面の共変微分を学んだので,すでに扱ったEgregium Theorem
すなわち,ガウス曲率$\frac{LN-M^2}{EG-F^2}$を第1基本量だけで表す式を見直してみよう.
これは
$\boldsymbol{f}_{ijk}-\boldsymbol{f}_{ikj}=0\cdots (*)$
より導き出されたことはすでに述べた.
ちなみに,$(*)$が曲面論の基本定理の可積分条件で,
その接平面成分がガウスの可積分条件で法線成分がコダッチの可積分条件である.
ここでは,ガウスの可積分条件を共変微分を用いて書き直す.
$( \ \ )^T$は接平面への正射影である.
なお,曲面の基本公式は
$\begin{cases}
\boldsymbol{f}_{ij}=\Gamma _{ij}^k\boldsymbol{f}_k+b_{ij}n \\
n_i=-b_{ij}g^{jk}\boldsymbol{f}_k\end{cases}$
である.
$\boldsymbol{f}_i=\partial _{u^i}$と表し
$\mathbb{R}^3$における$u^i$による微分を$d_{\partial _{u^i}}$と表す.
$\boldsymbol{f}_{ij}=d_{\partial _{u^j}}\partial _{u^i}$
$=D_{\partial _{u^j}}\partial _{u^i}+b_{ij}n$
$\boldsymbol{f}_{ijk}=d_{\partial _{u^k}}(D_{\partial _{u^j}}\partial _{u^i}+b_{ij}n)$
$(\boldsymbol{f}_{ijk})^T=D_{\partial _{u^k}}(D_{\partial _{u^j}}\partial _{u^i})+b_{ij}n_k$
ガウスの可積分条件は
$(\boldsymbol{f}_{ijk})^T-(\boldsymbol{f}_ikj)^T=0$
であるから
$D_{\partial _{u^k}}(D_{\partial _{u^j}}\partial _{u^i})+b_{ij}n_k-
D_{\partial _{u^j}}(D_{\partial _{u^k}}\partial _{u^i})-b_{ik}n_j=0$
したがって
$D_{\partial _{u^k}}(D_{\partial _{u^j}}\partial _{u^i})
-D_{\partial _{u^j}}(D_{\partial _{u^k}}\partial _{u^i})=-b_{ij}n_k+b_{ik}n_j\cdots (**)$
右辺は
$-b_{ij}n_k+b_{ik}n_j=b_{ij}b_{ks}g^{st}\boldsymbol{f}_t-b_{ik}b_{js}g^{st}\boldsymbol{f}_t$
さらに,$\boldsymbol{f}_l$との内積を取ると
$b_{ij}b_{ks}g^{st}g_{tl}-b_{ik}b_{js}g^{st}g_{tl}=b_{ij}b_{kl}-b_{ik}b_{jl}$
$(**)$の左辺を$R_{ijk}^{ \ \ \ \ \ \ s}\boldsymbol{f}_s$と表し,すなわち
$R_{ijk}^{ \ \ \ \ \ \ s}\boldsymbol{f}_s=D_{\partial _{u^k}}(D_{\partial _{u^j}}\partial _{u^i})
-D_{\partial _{u^j}}(D_{\partial _{u^k}}\partial _{u^i})$
とし
$R_{ijk}^{ \ \ \ \ \ \ s}\boldsymbol{f}_s \cdot \boldsymbol{f}_l=R_{ijk}^{ \ \ \ \ \ \ s}g_{sl}=R_{ijkl}$
とすれば
$R_{ijkl}=b_{ij}b_{kl}-b_{ik}b_{jl}\cdots (\sharp)$
となります.これがガウスの可積分条件です.
$(i,j,k,l)=(1,1,2,2)$とすれば
$R_{1122}=b_{11}b_{22}-b_{12}^2\cdots (\flat)$
となる.
ここで述べた$R_{ijkl}$を第1種のリーマン曲率テンソル量,$R_{ijk}^{ \ \ \ \ \ \ s}$を第2種のリーマン曲率テンソル量と呼ぶ.この定義は
書籍により異なるので注意する必要がある.
ガウスの可積分条件$(\sharp)$は見かけ上16個の式があるが,独立なのは$(\flat)$の1つだけである
ことを示すのはもう少し準備が必要です.
$R_{1122}$は曲面の共変微分だけで得られる式なので第1基本量だけで決まる式です.一方曲面のガウス曲率$K$は
$K=\dfrac{b_{11}b_{22}-b_{12}^2}{g_{11}g_{22}-g_{12}^2}=\dfrac{R_{1122}}{g_{11}g_{22}-g_{12}^2}$
と第1基本量だけで表すことができる.これがEgregium Theorem です.
さらに,$g_{11}g_{22}-g_{12}^2=EG-F^2$は$\boldsymbol{f}_1,\boldsymbol{f}_2$すなわち$\partial _{u^1},\partial _{u^2}$
の定める平行四辺形の面積の平方,すなわち,$\partial _{u^1},\partial _{u^2}$の定める平行四辺形の面積を$S$
とするとガウス曲率$K$は
$K=\dfrac{R_{1122}}{S^2}$
となる.この式によって,抽象曲面$\{U,I\}$でも
ガウス曲率が定義される.もちろん抽象曲面では図形的意味は持たなないが,.
ベクトルを連続して共変微分したときの差として利用される.
さて,ここでベクトルを連続して共変微分したときの差と述べたがこれを考える.
$X,Y,Z$を曲面上のベクトル場とする.
$D_XY-D_YX=[X,Y]$
が成り立つことはすでに述べた.
それでは
$D_Z(D_YX)-D_Y(D_ZX)$
はどうなるのか,すなわち共変微分の順番を変えたときの差が分からないようでは曲面上自由に共変微分が扱えるとは言えない.
この問題を解決するためにベクトルのテンソル積の理解が必要です.なおこの問題の解決の中で,ガウスの可積分条件がただ一つであることが示されます.
§4.1 ベクトルとテンソル
目次
全体の目次
|
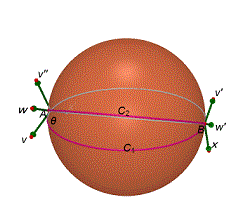 半径$1$の球面で考える.
半径$1$の球面で考える.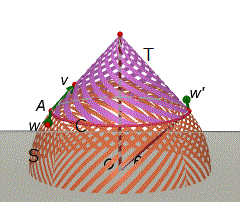 半径1の球面$S$の緯度$\theta$の緯線$C$で接する円錐$T$を考える(右図).
半径1の球面$S$の緯度$\theta$の緯線$C$で接する円錐$T$を考える(右図).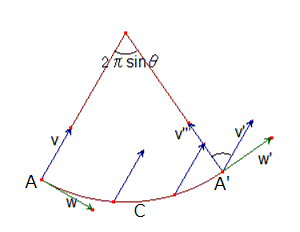 ここで,曲線$C$の接ベクトル$w$に注目する(平行ベクトル場ではない).$w,w'$は円を一周回っているから回転角は$2\pi$.
ここで,曲線$C$の接ベクトル$w$に注目する(平行ベクトル場ではない).$w,w'$は円を一周回っているから回転角は$2\pi$.