$\S12. \ $複素平面 2次元ユークリッド平面の合同変換は平行移動,回転移動,対称移動またはそれらの合成変換で,これらがユークリッド 幾何で重要な役割を演ずることは周知の通りである. ここでは,ポアンカレモデル$\mathbb{H}^+$の合同変換を扱う. これから扱うのは複素平面間の写像 $f:\mathbb{C}\longrightarrow \mathbb{C};z\mapsto \dfrac{az+b}{cz+d}$ である. 現在は高等学校で系統だった複素数の教育がなされているが, ここでこれから用いる複素数の基本事項をまとめておく. 以下考えるのは複素数平面であり,$i$は虚数単位である. 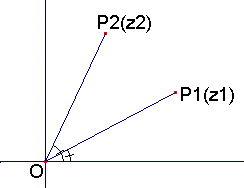 $1.$三角形の面積と内積 $O$は原点,$P_1(z_1),P_2(z_2)とする.$ $z_1=x_1+iy_1=r_1(\cos \theta _1+\sin \theta _1),$ $z_2=x_2+iy_2=r_2(\cos \theta _2+\sin \theta _2),$ のとき, $\arg (\bar{z_1}z_2)=\theta _2-\theta _1,|\bar{z_1}z_2|=r_1r_2$ であるから $\bar{z_1}z_2=(r_1r_2\cos (\theta _2-\theta _1),r_1r_2\sin (\theta _2-\theta _1))$ すなわち $\mathrm{Re} \bar{z_1}z_2=\overrightarrow{OP_1}\cdot \overrightarrow{OP_2},\mathrm{Im} \bar{z_1}z_2 =\overrightarrow{OP_1}\text{と} \overrightarrow{OP_2}\text{の決める平行四辺形の面積}$ となる.ただし$\mathrm{Re}z$は$z$の実部,$\mathrm{Im}z$は$z$の虚部である. これは成分で表した方が分かりやすいかもしれない. $\bar{z_1}z_2=(x_1-iy_1)(x_2+iy_2)$ $=(x_1x_2+y_1y_2)+i(x_1y_2-x_2y_1)$ 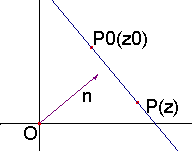 $2.$直線と円 複素数$n$に垂直で点$P_0(z_0)$を通る直線上の点を$P(z)$とおく. $P_0P=z-z_0$は$n$に垂直であるから $\dfrac{z-z_0}{n}\parallel i$ ただし$\parallel$は平行の意味. すなわち$\frac{z-z_0}{n}$は純虚数. $\therefore \dfrac{z-z_0}{n}+\dfrac{\bar{z}-\bar{z_0}}{\bar{n}}=0$ 通常は両辺に$|n|^2$をかけ $\bar{n}z+n\bar{z}=\bar{n}z_0+n\bar{z_0}$ 右辺は実数だから$2k$とおき $\bar{n}z+n\bar{z}=2k \ \ $ただし$k$は実数, 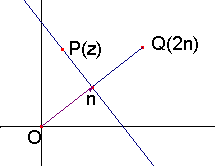 原点から直線に下した垂線の足を$n$とすると,上の式の$z_0$を$n$に置き換えればよいから $\dfrac{z}{n}+\dfrac{\bar{z}}{\bar{n}}=2$ すなわち $\bar{n}z+n\bar{z}=2|n|^2$ となる. この直線は,原点$O$,$Q(2n)$の垂直2等分線であるから $|z-2n|=|z|$ 両辺を平方して整理すると $\bar{n}z+n\bar{z}=2|n|^2$ となり一致する. $A(a)$を中心とする半径$r$の円の方程式は $|z-a|=r$ 両辺を平方して整理すると $z\bar{z}-\bar{a}z-a\bar{z}=r^2-|a|^2$ 両辺に実数をかけ円の方程式を $Az\bar{z}+\bar{B}z+B\bar{z}+C=0\cdots (\sharp)$ ただし,$A,C\in \mathbb{R},B\in \mathbb{C}$ と表すことが多い. さらに,$(\sharp)$は $(z+\dfrac{B}{A})(\bar{z}+\dfrac{\bar{B}}{A})=\dfrac{|B|^2-AC}{A^2}$ であるから,円の方程式は $Az\bar{z}+\bar{B}z+B\bar{z}+C=0$ ただし,$A,C\in \mathbb{R},B\in \mathbb{C},|B|^2-AC > 0$ となる. このように表せば,$(\sharp)$は$A\neq 0$のとき円で, $A=0$のとき直線となり,円と直線が統一的に扱える. 複素数平面で円を扱うときアポロニウスの円はしばしば用いられる. 定理 平面上に異なる2点$A,B$が与えれれている.このとき $PA:PB=m:n \ \ (m\neq n)$ を満たす点$P$の軌跡は,線分$AB$を$m:n$に内分する点, 外分する点を直径の両端とする円である. 証明 ベクトルを用いた方が見やすいので,ここではベクトルを用いて証明する. $A(\overrightarrow{a}),B(\overrightarrow{b}),P(\overrightarrow{p})$とする. $|\overrightarrow{p}-\overrightarrow{a}| :|\overrightarrow{p}-\overrightarrow{b}|=m:n$ より $n^2(\overrightarrow{p}-\overrightarrow{a})\cdot (\overrightarrow{p}-\overrightarrow{a})- m^2(\overrightarrow{p}-\overrightarrow{b})\cdot (\overrightarrow{p}-\overrightarrow{b})=0$ $\{n(\overrightarrow{p}-\overrightarrow{a})+m(\overrightarrow{p}-\overrightarrow{b})\} \cdot\{n(\overrightarrow{p}-\overrightarrow{a})-m(\overrightarrow{p}-\overrightarrow{b})\}=0$ $\{(n+m)\overrightarrow{p}-(n\overrightarrow{a}+m\overrightarrow{b})\} \cdot\{(n-m)\overrightarrow{p}-(n\overrightarrow{a}-m\overrightarrow{b})\}=0$ $\therefore \left(\overrightarrow{p}-\dfrac{n\overrightarrow{a}+m\overrightarrow{b}}{n+m}\right)\cdot \left(\overrightarrow{p}-\dfrac{n\overrightarrow{a}-m\overrightarrow{b}}{n-m}\right)=0$ $AB$を$m:n$に内分,外分する点をそれぞれ$C,D$とすれば $\overrightarrow{PC}\cdot \overrightarrow{PD}=0$ であるから.点$P$の軌跡は$CD$を直径とする円である. 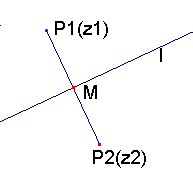 $3.$対称移動 2点$P_1(z_1),P_2(z_2)$が直線 $l:\bar{n}z+n\bar{z}=k \ \ $(ただし$k$は実数) に関して対称なとき,$z_1,z_2$の関係を求めよう. $P_1P_2$が直線$l$と垂直であるから $(z_1-z_2)\parallel n$ したがって $\dfrac{z_1-z_2}{n}-\dfrac{\bar{z_1}-\bar{z_2}}{\bar{n}}=0$ 線分$P_1P_2$の中点$M$が直線$l$上より $\bar{n}\dfrac{z_1+z_2}{2}+n\dfrac{\bar{z_1}+\bar{z_2}}{2}=k$ 2つの式を並べると $\begin{cases} \bar{n}(z_1-z_2)-n(\bar{z_1}-\bar{z_2})=0 \ \cdots (1) \\ \bar{n}(z_1+z_2)+n(\bar{z_1}+\bar{z_2})=2k \ \cdots (2) \end{cases}$ $(1)+(2)$は $\bar{n}z_1+n\bar{z_2}=k \cdots (3)$ $(1)-(2)$は $n\bar{z_1}+\bar{n}z_2=k \cdots (4)$ $(3),(4)$は同じ式である(片方はもう一方の共役をとったもの). 逆に$z_1,z_2$が$(3)$を満たすとき,$(4)$も満たすから,$(3)+(4)$及び$(3)-(4)$より $(1),(2)$を得る. したがって, 2点$P_1(z_1),P_2(z_2)$が直線$l$ $\bar{n}z+n\bar{z}=k$ に関して対称なとき,$z_1,z_2$の関係は $\bar{n}z_1+n\bar{z_2}=k$ であり.逆も成り立つ. すなわち,直線の方程式の$z,\bar{z}$のそれぞれに$z_1,z_2$を代入したもので 覚えやすい. 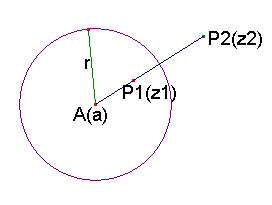 つぎに円に関する対称な点を定義する. 点$A(a)$を中心とする半径$r$の円を$A$とする.$A$と異なる点$P_1(z_1)$に対して, $P_2(z_2)$を半直線$AP_1$上で $AP_1\cdot AP_2=r^2$ を満たす点とする.このとき,点$P_1,P_2$を円$C$に関して対称であるという. ちなみに,この変換 $I(A,r):z_1\;\mapsto z_2$ を円$A$を反転円とする反転変換という. $P_1(z_1),P_2(z_2)$が点$A(a)$を中心とする半径$r$の円$A$に関して対称なとき, $|z_2-a||z_1-a|=r^2,\arg (z_2-a)=\arg (z_1-a)$ である.ここで, $\arg \dfrac{1}{z}=-\arg z,\arg \bar{z}=-\arg{z}$ に注意すれば $z_2-a=\dfrac{r^2}{\bar{z_1}-\bar{a}}$ となることがわかる. すなわち,円の方程式の$z,\bar{z}$にそれぞれ$z_1,z_2$を代入したもので,直線に関する対称な点と同じである. 直線,円に関しての対称点についてまとめると次のようになる. 定理 2点$P_1(z_1),P_2(z_2)$が直線,または円 $Az\bar{z}+\bar{B}z+B\bar{z}+C=0\cdots (\sharp)$ ただし,$A,C\in \mathbb{R},B\in \mathbb{C}$ に関して対称な必要十分条件は $Az_1\bar{z_2}+\bar{B}z_1+B\bar{z_2}+C=0$ である. ここで,円に関する対称移動である反転変換の性質を調べよう. 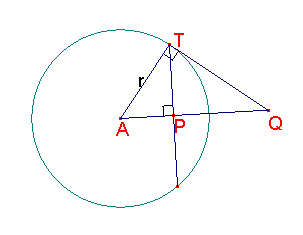 1. 円$A$に関して2点$P,Q$が対称なとき, $AP\cdot AQ=r^2$ より $AP:AT=AT:AQ$ したがって, $\triangle ATP$∽$\triangle AQT$ 円に関して対称な点は簡単に作図することができる. すなわち,$P$が与えられれば(円の内部), $P$を通り$AP$と垂直な直線と円との交点を$T$ とし,$T$における円の接線と$AP$との交点が$Q$. $Q$が与えらえたとき(円の外部),$Q$から円に接線$QT$を引き,接点から直線$AQ$ に下した垂線の足が点$P$. 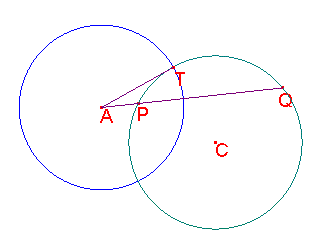 2. 円$A$に関して2点$P,Q$が対称なとき, $P,Q$を通る円は円$A$に直交する. $(\because)$ $P,Q$を通る円$C$と円$A$との交点の片方を$T$とする. このとき, $AP\cdot AQ=r^2$ であるから,直線$AT$は円$C$の接線である(接弦定理の逆). したがって,2円$A,C$は直交する. 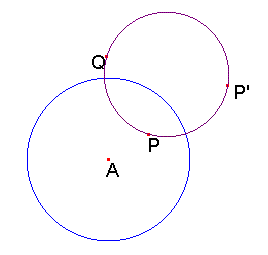 この性質を用いれば,2点$P,Q$と円$A$が与えられたとき,$P,Q$を通り円$A$ に直交する円は,$P$または$Q$の円$A$に関する対称点を求め,3点を通る円を作ればよいことがわかる. なお,2点$P,Q$が直線$l$に関して対称なとき,2点$P,Q$を通る円は,直線$l$に直交する.実際,$P,Q$を通る 円の中心は$P,Q$の垂直二等分線上すなわち直線$l$上にある. 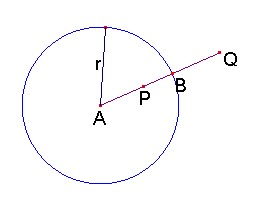 3. 次に,円$A$に関して2点$P,Q$が対称なとき,円$A$の半径を無限大にしてみよう. 半直線$AP$と円$A$の交点を$B$とする. このとき, $AP\cdot AQ=r^2$ より $(r-PB)(r+BQ)=r^2$ $BQ=\dfrac{r^2}{r-PB}-r=\dfrac{rPB}{r-PB}=\dfrac{PB}{1-\dfrac{PB}{r}}\to PB \ \ (r\to \infty)$ 半径無限大の円すなわち直線に関して の対称と通常の直線に関しての対称は同じであることがわかる. $4.$等角写像 ここでは,微分可能な複素関数の導関数の図形的意味を考える. 複素関数$f$が$z=z_0$で微分可能なとき $f(z)-f(z_0)=f'(z_0)(z-z_0)+\rho (z-z_0)$ とかける.ただし,$\rho (z-z_0)$は$z-z_0$の高位の無限小. したがって,$z$が$z_0$に十分近いとき $f(z)-f(z_0)\fallingdotseq f'(z_0)(z-z_0)$ ここで, $f'(z_0)=r(\cos \theta +i\sin \theta)$ とおくと $f(z)-f(z_0)\fallingdotseq r(\cos \theta +i\sin \theta)(z-z_0)\cdots (\sharp)$ すなわち,$z_0,f(z_0)$をそれぞれ原点とみれば, $f$は$\theta$の回転移動と$r$倍の相似変換の合成である. $f$は角度を保つことの説明は次に行いますが$(\sharp)$より$f$の局所的性質より 読み取った方が分かりやすいと思います. 微分可能な関数$f$が角度を保つことの一般的な説明は次のように行います. $f:\Omega (\subset \mathbb{C})\longrightarrow \mathbb{C}$ は微分可能で$f'(z_0)\neq 0$のとき $z_0$を通る2曲線$\phi _1(t),\phi _2(t) \ \ (\phi _1(0)=\phi _2(0)=z_0)$の交点$z_0$ における,2曲線のなす角は接線のなす角で $\arg \phi _2'(0)-\arg \phi _1'(0)$ である.一方,2曲線$\phi _1(t),\phi _2(t)$の$f$による 像$f(\phi _1(t)),f(\phi _2(t))$ の$f(z_0)$におけるなす角は $\dfrac{df(\phi (t))}{dt}=f'(\phi (t))\phi '(t)$ より $\arg f'(\phi _2(0))\phi _2'(0)-\arg f'(\phi _1(0))\phi _1'(0) =\arg \phi _2'(0)-\arg \phi _1'(0)$ このことから,交わる2曲線$\phi _1(t),\phi _2(t)$の交点$z_0$におけるなす角と$f$による像 $f(\phi _1(t)),f(\phi _2(t))$の交点$f(z_0)$におけるなす角は大きさは等しく, 向きも一致することがわかる. 以上述べてきたのは $f'(z_0)=r(\cos \theta +i\sin \theta)$ と表せるとき,すなわち$f'(z_0)\neq 0$のときである. $f'(z_0)=0$のとき成り立つとは限らない. 実際,$w=z^2$の原点において考える. 実軸,虚軸のなす角は$\frac{\pi}{2}$でともに実軸に移るから, 像のなす角は$\pi$である. 以上をまとめると次のようになる. 定理 $f(z)$が複素平面のある領域$D$で微分可能とする.$f(z)$は$f'(z)\neq 0$を満たす$z$ において等角である(角を保つ). ここで,円$|z-a|=r$に関する反転変換である $f(z)=\dfrac{r^2}{\bar{z}-\bar{a}}+a$ が等角であるかどうかを調べてみよう. 関数$f$を $z\mapsto z-a\mapsto \bar{z}-\bar{a}\mapsto \dfrac{r^2}{\bar{z}-\bar{a}}\mapsto \dfrac{r^2}{\bar{z}-\bar{a}}+a$ と分解する. 2番目の対応 $g(z)=\bar{z}$ だけが微分可能でない(Cauchy-Riemannの微分方程式を満たさない). しかし,これは実軸に関する対称移動で角度は保たれる. 対称移動は角は保つが向きは反対になる.すなわち,2曲線のなす角が$\theta$なら 対称移動後の2曲線のなす角は$-\theta$である. 他の変換はどれも微分可能で微分係数が$0$でないから 角度,向きともに同じである. したがって反転変換は角度は保たれるが向きが反対になることがわかる. 1次分数変換 目次に戻る 微分幾何 |